医療機関の経営の勘所

医療機関経営の特殊性 ― 株式会社との違い
病院や診療所など医療機関の経営は、一般の営利企業と大きく異なる側面を有しています。この特殊性を踏まえずに行う助言は、的外れになるおそれがあります。経営書籍やコンサルティングを活用する際も、まず医療機関特有の前提を確認することが重要です。
一般の営利企業の経営主体の多くは株式会社であり営利を目的としますが、医療機関の多くは医療法人(非営利)です。株式会社では株式過半の保有者が経営権を握りますが、医療法人では出資持分の多寡と経営権は原則無関係です。さらに、株式会社では誰でも経営者になれますが、医療法人では原則として医師のみが経営者(理事長)になれます。
株式会社の代表者は代表取締役、医療法人では理事長と呼称されます。前者が社長として会社業務を管理・執行するのに対し、後者は多くの場面で院長として医療機関の業務を管理・執行します。
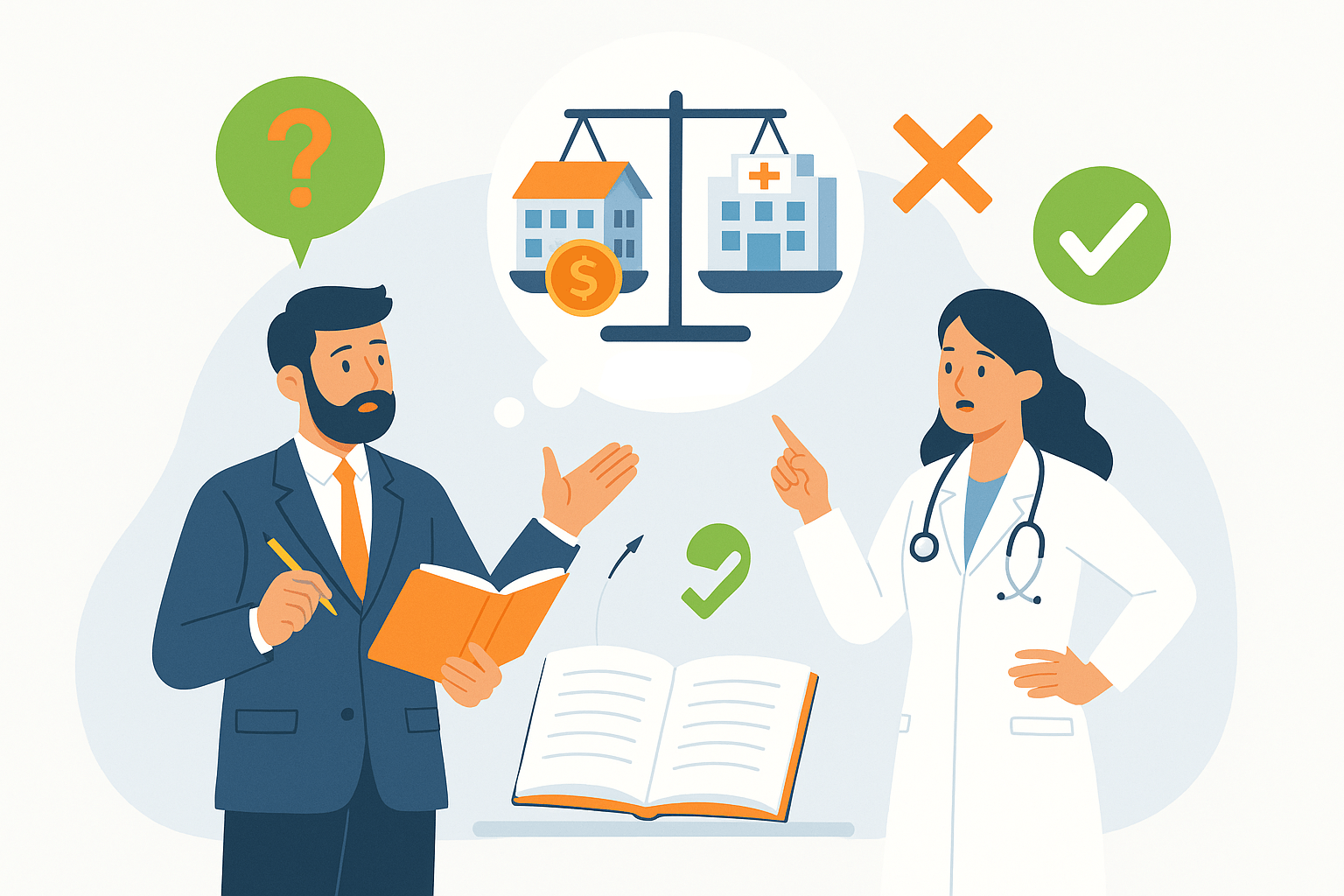
理事長と事務長の役割 ― 現場と経営の両立
病院では少なくとも100名超の職員を抱えることが多いにもかかわらず、理事長たる院長は最前線の診療に立ちながら経営を担うのが現実です。医師不足のなかで、院長が診療を離れて経営専念する体制は容易ではありません。
このため、理事長にとって経営数値の把握・組織運営の課題抽出・医療行政の最新動向を得るための有能な事務長の存在が不可欠となります。事務長は経理・人事労務といった基幹業務に加え、部門間の利害を調整する高いコーディネート力が求められます。優れた事務長を見いだし、育成することは、理事長の最重要課題の一つです。
人材確保が最大の経営課題 ― 医師・看護師の確保
医療機関の評価は、診療にあたる医師の資質に大きく依存します。優秀な医師を採用・定着させることは、経営者(医師)にとって常に最重要テーマです。
看護師の不足も深刻です。確保には、理事長だけでなく事務長を中心とする病院全体の総合力が必要となります。医療は本質的に労働集約型の産業であるため、良い人材を惹きつけ、活躍し続けてもらう環境整備が経営の要諦です。
以上のような医療機関特有の条件に配慮しつつ、経営の立て直しに取り組むことが真の再生につながります。
〔文責 片山卓朗〕
